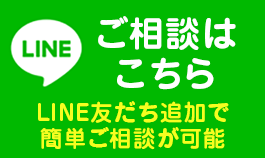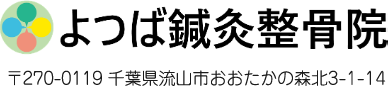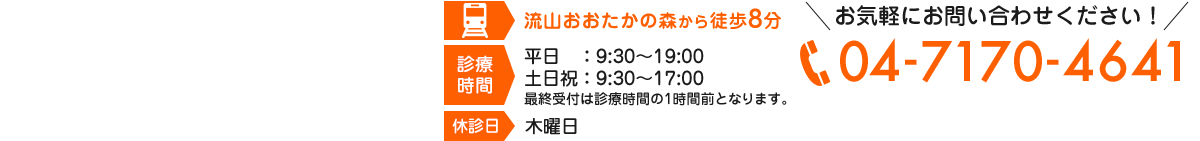Blog記事一覧 > 首・肩・うで・手 - よつば鍼灸整骨院の記事一覧
むちうち症とは?|流山市の交通事故後のサポートは、よつば鍼灸整骨院へ
むちうちとは、交通事故などによって首が激しく前後に振られた際に、首周辺の筋肉や靭帯、神経組織などが損傷を受けて発症するものです。この症状は、首の痛みだけにとどまらず、頭痛・めまい・倦怠感・肩こりなど、日常生活にも影響を及ぼすことがあるため注意が必要です。初期のうちに正しい治療を受けることで、後遺症のリスクを抑えることができます。
むちうちの主な症状とは|流山市で交通事故の治療をご希望の方へ
むちうちは、その症状が事故当日だけでなく数日後に出てくることも珍しくありません。代表的な症状は以下の通りです。
・首の違和感や痛み
・頭痛
・肩や背中のこり
・手足のしびれ
・めまいや吐き気
・集中力の低下
これらの症状に少しでも心当たりがある方は、早めの受診をおすすめします。流山市のよつば鍼灸整骨院では、交通事故によるむちうち症への対応を行っています。

なぜ早めの受診が重要なのか|流山市でむちうち治療を受けるならよつば鍼灸整骨院
交通事故後は、症状が軽く見えても内側ではダメージが蓄積しているケースが多くあります。「大したことない」と思っても、後から症状が悪化する可能性があるため、事故直後の受診が大切です。流山市内で信頼できる整骨院をお探しなら、よつば鍼灸整骨院へお越しください。お身体の状態をしっかりと確認し、的確な施術をご提案いたします。
まとめ|交通事故後の身体のケアは流山市のよつば鍼灸整骨院で
交通事故によるむちうちは、軽視せず適切なタイミングでの治療が必要です。痛みや不調が慢性化する前に、しっかりとケアを行いましょう。流山市にお住まいの方で交通事故後の不調を感じている方は、ぜひよつば鍼灸整骨院までお越しください。患者様一人ひとりに寄り添ったサポートで、安心して通院していただける環境を整えております。

【流山市のよつば鍼灸整骨院|首コリについて】
日常生活でこんな首の不調にお困りではありませんか?
・首が重く、朝からスッキリしない
・首のこりと一緒に目の疲れや頭痛がある
・姿勢が悪く、猫背気味なのが気になる
・疲れがたまると首が張って吐き気が出る
・病院では異常がないと言われたが不調が続いている
こうした原因のはっきりしない首こりにお悩みの方が多数来院されています。
姿勢のゆがみや自律神経の乱れ、生活習慣による筋緊張が隠れた要因となっている場合があります。
【目次】|流山市のよつば鍼灸整骨院
・首こりの背景と症状
・姿勢と筋緊張の関係
・当院の施術アプローチ
・流山市で首こりを改善したい方へ
・よくあるご質問
首こりの背景と症状|流山市のよつば鍼灸整骨院
首こりには以下のような背景があります
・首の筋肉に持続的な緊張がかかっている
・デスクワークやスマホ操作による“うつむき姿勢”の習慣
・血流が悪くなり、頭部への循環不良が起こる
・疲労やストレスで交感神経が優位になっている
その結果、首のこりに加えて頭痛・耳鳴り・めまいなどを伴うケースもあります。
流山市では、在宅ワークや育児による姿勢の崩れが背景にある患者様が多く、首・肩まわりの筋肉に無理な負担がかかっている方が目立ちます。
姿勢のクセによって筋緊張が慢性化し、首のこりが“当たり前”になっている人が多いのです。
施術アプローチ|流山市のよつば鍼灸整骨院
当院では、次のような内容で症状の改善を行っております。
・首の動きと筋バランスを評価
・姿勢バランスの調整(骨盤〜頸椎)
・首肩まわりの深部筋をやわらげる整体手技
・自律神経を整える鍼灸・温熱療法
・在宅環境に合ったストレッチや姿勢指導
その場しのぎではなく、再発しにくい体作りを目指すのが特徴です。
流山市で首こりを改善したい方へ
「薬に頼らず体質から改善したい」
そんなあなたに、よつば鍼灸整骨院は姿勢と神経の両面から整える施術でしっかりとサポートいたします。
まずは今の状態をチェックし、一緒に根本改善を目指していきましょう。
よくあるご質問|流山市のよつば鍼灸整骨院
- マッサージ店との違いは何ですか?
- 当院は国家資格を有した施術者が原因を評価しながら構造的にアプローチします。
朝起きたら首が痛い…寝違えにお困りの方へ|よつば鍼灸整骨院(流山市おおたかの森)
「朝起きたら首が動かない」「横を向こうとするとピキッと痛む」
そんな**寝違え(首の急な痛み)**は、無理に動かすことで悪化してしまうことがあります。
よつば鍼灸整骨院では、痛みの少ない鍼灸施術と丁寧なケアで、首の可動域を少しずつ回復させながら、早期の改善を目指します。

🔹寝違えの施術内容(初診:約60分)|よつば鍼灸整骨院
1️⃣ カウンセリングとチェック(約10分)
よつば鍼灸整骨院ではまず、痛みが出たタイミングや首の動きに関するお悩みを丁寧に伺います。
前後・左右・上を向く動きの確認を行い、どの角度で痛みが出るかを確認します。
🔍 よくあるお悩み例:
・首を後ろに倒せない
・振り向けないほど片側の首が固まっている
・肩や背中まで張ってくる感じがある
2️⃣ 首・肩・背中周辺をやさしくほぐす(約10〜15分)
筋肉が固まっている部分を中心に、無理のない範囲で血流を促しながら緊張をゆるめていきます。
痛みの出ている部分は避けて、関連する筋肉にやさしくアプローチします。
3️⃣ 鍼で深いこわばりを改善(約20〜25分)
痛みの元になっている首や肩の深部にこわばりがある場合、細く痛みの少ない鍼を使用して、ピンポイントで緊張をゆるめていきます。
状態により、首だけでなく背中や肩甲骨周辺まで施術することもあります。
※必要に応じて、お灸で温めながら血流改善を図る場合もあります。
4️⃣ 施術後のアドバイス(約10分)
施術後は、痛みをぶり返さないようにするための動き方・姿勢・生活での注意点をお伝えしています。
💡よつば鍼灸整骨院でよくお伝えするアドバイス例:
・痛い側を無理に振り向かない
・首を強く回さない
・痛みの出はじめは冷やし、2日目以降は温める
🔻寝違え:回復までの目安(よつば鍼灸整骨院の施術目安)
症状に応じて、以下のような回復スピードが一般的です。
✅ 軽度(少し動かしにくい):1〜3日
→ 初期に施術すれば1回でかなり楽になるケースも多いです。
✅ 中度(振り向けない・動きが制限されている):3〜7日
→ 2〜3回の施術でスムーズに動けるようになります。
✅ 重度(首が固まって動かない・強い痛み):1週間〜10日以上
→ 炎症を抑えながら徐々に可動域を回復し、再発防止のケアも行います。
よつば鍼灸整骨院では、再発予防として姿勢改善や簡単なストレッチ法の指導も行っています。
📍半個室空間・お子様連れOK!
よつば鍼灸整骨院では仕切りのある施術スペースをご用意しておりますので、まわりの目を気にせずリラックスして施術を受けられます。
小さなお子様連れでもお気軽にご来院ください。
「様子を見ていたけど痛みが変わらない」「薬や湿布だけでは不安…」
そんなときは、よつば鍼灸整骨院の優しい鍼灸施術で早めのケアをおすすめします!
肩こり・頭痛でお悩みの方へ|よつば鍼灸整骨院(流山市おおたかの森)
:-おへそから指幅3本分外側で、左右にある。-大巨(だいこ):-天枢から指3本分下で、左右にある。-2-724x1024.png)
デスクワークや長時間の同じ姿勢が続くと、肩や首の筋肉が固まり、血流が悪くなることで頭痛や目の疲れにつながることがあります。特に「肩こりと一緒に頭痛がある」というお悩みを多く伺います。
よつば鍼灸整骨院では、痛みの少ない鍼施術で筋肉の緊張を緩め、肩こりや頭痛を根本から改善へ導きます。
🔹施術の流れ(初診:約60分)🔹
1️⃣カウンセリング・チェック(約10分)
まず、肩こりや頭痛の状態を詳しくお聞きし、姿勢・可動域・筋肉の硬さをチェックします。
例えば…
✔ 頭痛が出るのは朝?それとも仕事終わり?
✔ デスクワーク中、無意識に肩をすくめていないか?
✔ 肩だけでなく、首や後頭部の筋肉がガチガチに固まっていないか?
特に「首の付け根(後頭部)が痛む・重い」という方は、肩こりによる緊張型頭痛の可能性が高いため、首と肩の筋肉を重点的にチェックします。
2️⃣筋肉をほぐし、血流を促す施術(約15分)
鍼を打つ前に、固まった筋肉をやさしくほぐし、血流を改善します。特に、首・肩・肩甲骨周りの筋肉にアプローチし、緊張をゆるめます。
3️⃣痛みの少ない鍼でコリと頭痛の原因にアプローチ(約25分)
肩こりと頭痛の原因となるポイントに細い鍼を打ち、深部の筋肉を緩めます。
🔸 施術例:肩こり+頭痛がある場合
✅ 後頭部からこめかみにかけて頭痛がある方
→ 首の後ろ(後頭下筋群)や側頭部のツボに鍼をして、筋肉の緊張を緩和。
✅ 肩がこると目の奥が重くなる方
→ **首・肩の筋肉(僧帽筋・肩甲挙筋)**にアプローチし、目の疲れも軽減。
✅ 肩こりがひどく、腕や手がしびれる方
→ 首から肩、腕につながる神経の流れを改善するため、頚椎(首の骨)周りの緊張をゆるめます。
※症状によっては、お灸を使い、冷えや血行不良を改善することもあります。
4️⃣施術後のアドバイス(約10分)
施術後は、肩こり・頭痛を繰り返さないための姿勢のポイントやセルフケアをお伝えします。
🔹 日常で気をつけること
✔ デスクワーク中の姿勢のコツ(肩をすくめない、背中を丸めない)
✔ 仕事の合間にできる簡単なストレッチ
✔ 首・肩の負担を減らす枕の選び方。
肩こりや頭痛を根本からケアし、快適な毎日を過ごしませんか?
📍よつば鍼灸整骨院|流山市おおたかの森
こんにちは!
よつば鍼灸整骨院です!
【寒さによる首肩腰の痛みに注意⚠】
急に冬らしく寒さが辛くなってきました。
寒いと人の筋肉は硬くなり、血流が悪くなることで痛みや動きの悪さから疲れやすくなったりします。
まずは体を冷やさないことと、軽くでもいいので体温が上がるような運動を行うことが重要になるのですが、筋肉が硬いと怪我の元になってしまうので、身体の筋肉をほぐして、痛みや辛さをとるようにすることが大事です。
筋肉が硬くなると血行が悪くなり、高血圧になったり、脳梗塞や心筋梗塞のリスクが高くなりますので
思い当たる方は早めのケアをしましょう。
当院では、体の筋肉をほぐし、ラジオ波やハイボルトで身体の姿勢や状態を整えます。
場合によっては自律神経も緊張していて辛くなることもあるので、緊張やストレスをとり除く治療を行っていきます。
ぜひ当院にご相談ください。

背中の痛みについて
背中の痛みは、多くの人が日常生活の中で一度は経験する症状です。痛みの程度や原因はさまざまで、軽い違和感から動くことが困難になるほどの強い痛みまで幅広く見られます。よつば鍼灸整骨院では、個々の症状に合わせた適切な施術を提供し、早期の改善を目指しています。

背中の痛みの主な原因
- 筋肉の緊張や疲労
長時間のデスクワークや同じ姿勢を続けることで、背中の筋肉が緊張し、痛みが発生します。特に肩甲骨周辺や背骨沿いの筋肉が固くなることが多いです。 - 姿勢の悪さ
猫背や反り腰など、正しい姿勢を保てないことが背中の負担を増加させ、慢性的な痛みの原因となります。 - ストレス
精神的なストレスは筋肉の緊張を引き起こし、特に背中や肩周りに影響を及ぼします。 - 外傷やスポーツによる負傷
スポーツ中の怪我や、日常生活での不意の動作による筋肉や関節の損傷が痛みを引き起こすことがあります。 - 内臓疾患
まれに、腎臓や肺、心臓などの内臓疾患が背中の痛みとして現れることもあるため、痛みが長期間続く場合は医師の診断が必要です。
よつば鍼灸整骨院の施術方法
よつば鍼灸整骨院では、患者様の症状や原因に応じた多様な施術を行っています。
- 手技療法(マッサージ・指圧)
筋肉の緊張を和らげ、血行を促進することで痛みを軽減します。 - 鍼灸治療
経絡やツボを刺激することで、自然治癒力を高め、痛みの根本的な改善を図ります。 - 電気療法
低周波治療器を使用して、深部の筋肉にアプローチし、痛みの緩和を促進します。 - 姿勢矯正
骨格の歪みを調整し、正しい姿勢を取り戻すことで再発を防ぎます。 - ストレッチ指導
日常生活で取り入れやすいストレッチを指導し、自宅でもケアができるようサポートします。
施術の流れ
- カウンセリングと問診
まず、痛みの場所や強さ、生活習慣について詳しくお聞きします。 - 身体の状態チェック
姿勢や可動域、筋肉の状態を確認し、痛みの原因を特定します。 - 施術プランのご提案
患者様の症状に最適な施術プランを提案し、納得いただいた上で施術を開始します。 - 施術
症状に応じた施術を丁寧に行い、痛みの緩和と再発防止を目指します。 - アフターケアとアドバイス
施術後の過ごし方や、自宅でできるセルフケアをアドバイスします。
背中の痛みにお悩みの方は、ぜひ一度よつば鍼灸整骨院へご相談ください。専門のスタッフが丁寧に対応し、痛みの改善を全力でサポートいたします。
胸郭出口症候群とは?
胸郭出口症候群(きょうかくでぐちしょうこうぐん)は、首から腕にかけて走る神経や血管が圧迫されることによって、腕や手にしびれや痛み、脱力感などの症状を引き起こす疾患です。特に、デスクワークや重いものを持つ仕事、姿勢が悪い方に多く見られます。

胸郭出口とは?
胸郭出口とは、首の付け根から鎖骨の下を通って腕に向かう神経や血管が通る部分を指します。この部位は、以下の3つの通路に分けられ、それぞれで圧迫が起こることで症状が現れます。
- 斜角筋隙(しゃかくきんげき):首の前斜角筋と中斜角筋の間を通る部分
- 肋鎖間隙(ろくさかんげき):鎖骨と第一肋骨の間
- 小胸筋下隙(しょうきょうきんかげき):小胸筋の下を通る部分
症状
胸郭出口症候群の主な症状は以下の通りです。
- 腕や手のしびれ・痛み:特に小指や薬指に症状が出やすい
- 肩や首のこり:長時間の同じ姿勢で悪化しやすい
- 腕の脱力感:物を持ったときに力が入りにくい
- 冷えや血行不良:血管が圧迫されると手先が冷えやすくなる
症状は、腕を上げたり、肩を後ろに引いたときに悪化しやすいのが特徴です。
原因
胸郭出口症候群は、以下のような要因によって発生します。
- 姿勢の悪化:猫背や巻き肩などが神経や血管を圧迫しやすくする
- 筋肉の過緊張:首や肩の筋肉が硬くなることで圧迫が起こる
- 骨格の異常:鎖骨や第一肋骨の位置異常
- スポーツや仕事の影響:重量物の持ち運び、長時間のデスクワークなど
診断と検査
胸郭出口症候群の診断には、以下の検査が行われます。
- Morley(モレー)テスト:鎖骨上部を押して症状が出るか確認
- Adson(アドソン)テスト:腕を外旋・伸展させ、脈が減弱するか確認
- Roos(ルース)テスト:腕を90度挙げて開閉運動し、症状が出るか確認
治療方法
胸郭出口症候群の治療は、主に保存療法が中心です。
1. 姿勢改善
姿勢の悪化が原因の一つなので、正しい姿勢を意識することが大切です。特にデスクワーク時は、肩を開き、首をまっすぐ保つようにしましょう。
2. ストレッチ・運動療法
胸郭出口部分の圧迫を減らすために、以下のストレッチや運動を行います。
- 斜角筋のストレッチ:首を横に倒してストレッチ
- 小胸筋のストレッチ:壁に手をついて胸を開く
- 肩甲骨の運動:肩を回したり、肩甲骨を寄せる運動
3. 鍼灸・整体施術
流山市おおたかの森のよつば鍼灸整骨院では、胸郭出口症候群に対する施術として、以下の方法を取り入れています。
- 筋肉の緊張を和らげる鍼灸施術
- 姿勢を整える整体・骨格調整
- 神経の圧迫を軽減するマッサージ
症状が慢性化している場合は、継続的な施術と生活習慣の改善が必要になります。
TFCC損傷(三角繊維軟骨複合体損傷)

千葉県流山市でお悩みの症状を改善したい方へ よつば鍼灸整骨院では、肩こりや腰痛、スポーツ障害など様々な症状に対応しております。豊富な専門知識と確かな技術で患者様の症状に合わせた最適な施術を行いますので、ぜひ一度ご相談ください。
TFCC損傷(三角繊維軟骨複合体損傷)とは、手首の小指側にある靱帯や軟骨などの組織が損傷する怪我です。
手首をひねったり、ドアノブを回したりする動作時に痛みや不安定感が出現します。
TFCC損傷(三角繊維軟骨複合体損傷)の症状
小指側の手首の痛み
・手首の小指側(尺骨側)に鋭い痛みや鈍い痛みを感じるのが最も一般的な症状
・痛みは特に手首を回す動作(例、ドアノブを回す、ボトルの蓋を閉めるなど)
手首の不安定感
・TFCC(三角繊維軟骨複合)は手首の安定性を高めるため、損傷したときに手首が不安定に感じたり、ぐらつく感覚感じるようになる
腫れや圧痛
・主に手首の小指側の痛みや腫れが著明
・損傷部分を触ると痛みが増す(圧痛)、また手首を動かした際に「クリック音」や「カチッ」という音を感じる
握力の低下
・手首の痛みや不安定感の影響で握力が弱くなる
・特に重いものを持つ際や長時間使う動作で不快感が強くなる
TFCC損傷(三角繊維軟骨複合体損傷)の症状
慢性的なストレスが原因による原因
繰り返し負担がかかるスポーツ
・野球:バットを振る動作
・テニス:ラケットを振る動作
・ゴルフ:クラブを振る動作
日常生活での反復動作
・タイピング:長時間のキーボード操作
・手芸や裁縫:手首を使う繰り返し動作
・鍵開け:頻繁な鍵の回転動作
職業上の負担
・配管工や大工:工具の使用や重い物の持ち上げ動作
・美容師:ハサミやドライヤーを使い続ける動作
急性的な外傷による原因
転倒や衝突
・転倒時に手をつく
・スポーツ中の衝突
強い捻じれ動作
・重い物を急に持ち上げる
・激しい運動やスポーツ中の手首の捻じれ
交通事故
・ハンドルの強い握りや跳ね返り
他の急性外傷
・直接的な打撃
その他の原因
加齢による変性
・年齢とともにTFCC(三角繊維軟骨複合)の組織が弱くなる
手首の構造
・生まれつき手首の構造がTFCC(三角繊維軟骨複合)に負担をかけやすい場合
よつば鍼灸整骨院での施術内容
よつば鍼灸整骨院では、TFCC損傷(三角繊維軟骨複合体損傷)の症状を改善するために、以下のような治療を行っています。
➀手技療法(マッサージ・ストレッチ)
②アイシング療法
③ハイボルト治療、ラジオ波治療、鍼治療、運動指導等
④テーピング
TFCC損傷(三角繊維軟骨複合体損傷)にお悩みの方は、流山市にあるよつば鍼灸整骨院にご相談ください。
当院の専門スタッフが、患者様一人一人に合った最適な治療法を提供し、根本的な原因を取り除くお手伝いをします。
運動療法やストレッチ、日常生活のアドバイスを通じて、TFCC損傷(三角繊維軟骨複合体損傷)の症状を改善し、再発防止のサポートをいたします。
TFCC損傷(三角繊維軟骨複合体損傷)は、手首の小指側にある靭帯や軟骨などの組織が損傷する疾患で、転倒やスポーツ、手首の使いすぎなどが原因で発症することが多いですが、適切なケアと予防策を講じることで、痛みから解放され、快適な運動生活を送ることが可能です。
お悩みを解消し、健康的な生活を取り戻しましょう。お待ちしております。
肘部管症候群

千葉県流山市でお悩みの症状を改善したい方へ よつば鍼灸整骨院では、肩こりや腰痛、スポーツ障害など様々な症状に対応しております。豊富な専門知識と確かな技術で患者様の症状に合わせた最適な施術を行いますので、ぜひ一度ご相談ください。
肘部管症候群とは、肘内側の尺骨神経が圧迫され適切に働かないことで薬指や小指から肘にかけてのしびれや痛みで生じる症状です。
初期段階では、しびれや軽い痛みが主な症状ですが、進行すると手や指の筋力が低下し、物をしっかりつかむことが難しくなります。重症になると、指が曲がったままの状態(鷲手)になることもあります。
夜間や長時間肘を曲げている状態で症状が悪化することが多く、日常生活に影響を与えることがあります。早期の診断と治療が重要で、適切なケアにより症状の進行を防ぐことが可能です。
肘部管症候群の原因
変形性関節症
・肘関節の変形が進行すると、肘部管が狭くなり尺骨神経が圧迫されます。骨のトゲ(骨棘)が原因となることもあります。
外傷
・肘の打撲や骨折などの外傷により、肘部管が狭窄し尺骨神経が圧迫されることがあります。過去の外傷が神経圧迫の原因として残ることもあります。
ガングリオン
・腱鞘や関節包から生じるガングリオンという腫瘤が肘部管内で尺骨神経を圧迫することがあります。
反復動作や姿勢
・肘を頻繁に曲げ伸ばしする動作や、長時間同じ姿勢を保つことで尺骨神経に負担がかかることがあります。例えば、長時間のパソコン作業や電話の受話器を耳に挟んで話す姿勢が影響することがあります。
解剖学的な要因
・一部の人は、生まれつき肘部管が狭く尺骨神経が圧迫されやすいことがあります。神経の周囲の構造が通常よりも狭い場合、これが原因となることが考えられます。
肘部管症候群の症状
・薬指や小指から肘にかけてのしびれ
肘部管症候群の初期症状として最も多く見られるのが、薬指や小指から肘にかけてのしびれです。
神経が圧迫されることで、これらの部位に異常な感覚やしびれが発生します。
・薬指や小指から肘にかけての痛み
しびれに伴って、同じ部位に痛みが発生することもあります。この痛みは時には鋭く、日常生活の動作を行う上で支障をきたすことがあります。
・手や指の筋力低下
肘部管症候群が進行すると、手や指の筋力が低下します。特に指を使った細かい作業が困難になり、物をしっかりとつかむことが難しくなることがあります。
・鷲手(指が曲がったままの状態)
重症になると、尺骨神経の機能障害が進行し、指が曲がったままの状態(鷲手)になることがあります。この状態は、指を伸ばす筋肉が弱まることで発生します。
・夜間や長時間の肘の曲げる状態で症状が悪化
長時間肘を曲げた状態や夜間に症状が悪化することが多く見られます。例えば、電話の受話器を長時間持って話すことや、パソコンでの作業、寝ている間に肘が曲がった状態が続くといった状況で症状が悪化することがあります。
・日常生活の動作(例:電話の受話器を持つ、パソコン作業)に支障
日常生活の様々な動作が困難になることがあります。例えば、ドアノブを回す、カバンの持ち手を掴む、キーボードを打つなど、普段何気なく行っている動作に影響が出ることがあります。
よつば鍼灸整骨院での施術内容
よつば鍼灸整骨院では、肘部管症候群の症状を改善するために、以下のような治療を行っています。
➀手技療法(マッサージ・ストレッチ)
②アイシング療法
③ハイボルト治療、ラジオ波治療、鍼治療、運動指導等
④テーピング
肘部管症候群にお悩みの方は、流山市にあるよつば鍼灸整骨院にご相談ください。
当院の専門スタッフが、患者様一人一人に合った最適な治療法を提供し、根本的な原因を取り除くお手伝いをします。
運動療法やストレッチ、日常生活のアドバイスを通じて、肘部管症候群の症状を改善し、再発防止のサポートをいたします。
肘部管症候群は、小指と薬指がしびれ、進行すると手内の筋の筋萎縮によりお箸が持ちにくくなり、細かいものがつまみにくくなってしまいます。
しかし当院で適切なケアと予防策を講じることで、痛みから解放され、快適な運動生活を送ることが可能です。
お悩みを解消し、健康的な生活を取り戻しましょう。お待ちしております。
頚椎ヘルニア

千葉県流山市でお悩みの症状を改善したい方へ よつば鍼灸整骨院では、肩こりや腰痛、スポーツ障害など様々な症状に対応しております。豊富な専門知識と確かな技術で患者様の症状に合わせた最適な施術を行いますので、ぜひ一度ご相談ください。
頚椎ヘルニアとは首の骨(頚椎)間にある椎間板が変性し、その内部の組織が外に飛び出すことで、近くの神経を圧迫し、さまざまな症状を引き起こす疾患です。
この状態は、首や肩の痛み、手足のしびれなど、日常生活に支障をきたす症状を伴うことがあります。
頸椎ヘルニアの原因
①加齢による椎間板の機能低下
・年齢とともに椎間板の弾力性が低下し、外部からの衝撃や圧力に対する耐性が弱まる
② 不適切な姿勢や生活習慣
・長時間のデスクワークやスマートフォンの使用など首に負担をかける姿勢が続くことで、椎間板にストレスが蓄積する
③ 外傷や過度な負荷
・交通事故やスポーツによる首への強い衝撃
・重い物を持ち上げる際の無理な動作
④ 遺伝的要因
・家族に椎間板ヘルニアの歴史がある場合、発症リスクが高まる
頸椎ヘルニアの症状
①首や肩の痛み
・首の後ろや肩甲骨周辺に痛みやこりを感じる
② 腕や手のしびれ・痛み
・神経の圧迫により、腕や手にしびれや痛みが放散する
③ 筋力低下
・手や腕の筋力が低下し、物を握る力が弱くなる
④ 感覚異常
・手や指先にチクチクとした感覚や、感覚が鈍くなる
⑤ 下肢の症状
・重度の場合、足のしびれや歩行の不安定
・排尿、排便の障害が現れる
よつば鍼灸整骨院での施術内容
よつば鍼灸整骨院では、頸椎ヘルニアの症状を改善するために、以下のような治療を行っています。
➀手技療法(マッサージ・ストレッチ)
②アイシング療法
③ハイボルト治療、ラジオ波治療、鍼治療、運動指導等
④テーピング
頸椎ヘルニアにお悩みの方は、流山市にあるよつば鍼灸整骨院にご相談ください。
当院の専門スタッフが、患者様一人一人に合った最適な治療法を提供し、根本的な原因を取り除くお手伝いをします。
運動療法やストレッチ、日常生活のアドバイスを通じて、頸椎ヘルニアの症状を改善し、再発防止のサポートをいたします。
頸椎ヘルニアは、加齢や悪い姿勢、外傷、遺伝、喫煙などが原因ですが、適切なケアと予防策を講じることで、痛みから解放され、快適な運動生活を送ることが可能です。
お悩みを解消し、健康的な生活を取り戻しましょう。お待ちしております。